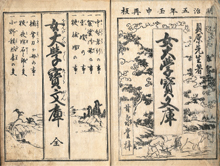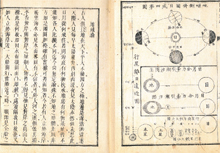第2章
2010年度男女共同参画推進重点項目および活動報告
第4節 学内外における男女共同参画ネットワークの構築
1.地域ネットワーク
地域ネットワークに関する活動として、「名古屋市男女平等参画推進会議(イコールなごや)」(平成22年7月1日、平成23年2月14日)に参加した。本会議は、男女共同参画社会の形成の促進を図るため平成9年に設置され、女性団体、経営者団体、労働者団体地域団体、教育団体、マスコミ、有識者、行政機関等43名の委員より構成されており、それぞれの立場から男女平等参画を推進するとともに、情報及び意見を交換し、その他必要な連携を図っている。平成22年度は、以下の議事・報告がなされた。
「名古屋市女性の活躍推進企業認定・表彰制度」の企画委員会が設置され、女性がいきいきと活躍できるような取組をしている企業の認定、特に優れた企業及び模範となる個人に対して表彰する制度が検討された。平成22年度は、表彰企業3社、認定企業4社、個人表彰4名が選定された。また、平成22年9月には、第7回男女平等参画に関する基礎調査に関する調査結果速報が提出された。これは、名古屋市が男女平等参画に関する意識や実態を把握するために5年ごとに実施している調査であり、(Ⅰ)男女平等参画意識および家族について、(Ⅱ)地域活動について、(Ⅲ)労働について、(Ⅳ)人権に関わる問題についての設問項目が調査対象となった。労働については、「女性が職業を持つことについてあなたはどうお考えですか」との質問に対し、全体としては「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」(再就職型)とする人が男女とも4割超と最も多いのに対し、20歳代女性では「子どもができてもずっと職業を持ち続けるほうがよい」(継続型)が41.4%と再就職型37.1%を上回った。愛知労働局からは、育児・介護休業法に関する相談が前年の2,3倍に急増しており、「改正育児・介護休業法の周知及び施行」など仕事と家庭を守るための対策が平成22年度雇用均等行政の最重点項目の一つとしてあげられたとの報告もあった。名古屋市は、推進してきた「男女共同参画プラン21(平成13年5月策定)」の計画期間が平成22年度で満了することから、5つの目標(目標1:男女の人権の尊重、目標2:男女平等・男女自立のための意識改革、目標3:方針決定過程への女性の参画、目標4:雇用等における男女平等、目標5:家庭・地域における男女の自立と平等参画)と4つの重点項目(1:女性に対するあらゆる暴力を根絶する、2:男女平等参画の理解を定着させる、3:男女がともに仕事と家庭・地域生活とを調和させることを支援する、4:名古屋市役所における男女平等参画を一層すすめる)からなる新しい計画(計画期間平成23〜27年度)を策定しており、市民の誰もが性別に関わらず安心して豊かに暮らせる社会をめざす計画を示した。
2.大学間ネットワーク
名古屋大学における男女共同参画に関する情報提供として、「大学教育改革フォーラム in 東海 2011」(平成23年3月12日、名古屋大学IB電子情報館)で、以下のポスター発表を行った。
●ポスター題目「名古屋大学における男女共同参画の取り組み
〜仕事と育児の両立支援を中心に〜」 |
| ●発表要旨 |
| |
2003年に設置された名古屋大学男女共同参画室は、現在、子育て支援、ポジティブ・アクション、女子学生エンカレッジ、産学官連携などの事業に取り組んでいます。なかでも仕事と育児の両立支援については、2006年の東山地区「こすもす保育園」開園以降、2009年には同園の拡張と鶴舞地区「あすなろ保育園」の新設、さらに、常設としては全国初となる大学内学童保育所「ポピンズアフタースクール」を開校し、子育て中の女性研究者がキャリアを継続できるよう、全学を挙げて支援体制を整備しつつあります。
今回の発表では、こうした名古屋大学の取り組みを、近隣の大学の方々にも参考にしていただけるよう、具体的な事例とともにご紹介します。
|
当日はお昼休みを利用してのポスターセッションで、現在入校対象となっている近隣大学の方々に、ポピンズアフタースクールの特徴を紹介説明した。

3.学内女性研究者ネットワーク
女性研究者ネットワーク構築として、女性研究者懇話会、職員組合女性部、男女共同参画室の共催で、女性教職員を対象とした「秋の学習会」を開催した。
| ●テーマ「先駆者の気概に学ぶ 〜“知”の継承から考える明治期の女性教育〜 |
| ●講 師 榊原千鶴(男女共同参画室員) |
| ●講 座 |
| |
(1)平成22年10月28日(木)12時〜13時
青山千世 〜胸を張って、新しい時代を一歩ずつ〜
(2)平成22年11月10日(水)12時〜13時
美子皇后 〜改革の担い手、「宮中のたましい」と呼ばれて〜
(1)平成22年11月18日(木)12時〜13時
若江薫子 〜皇后の家庭教師、「あっぱれ宏才の人」〜
|
お昼休みの時間を利用し、昼食を取りながらの講座として開催した。日本が近代国家として歩み始めた時期に学び始めた女性、あるいは、その後の女性教育に大きな影響を与えた女性を取り上げ、日本の女性教育史の一端を、資料とともに解説した。いずれも参加者は10名前後であり、解説の後に設けた質疑応答の時間には、当時の女性たちの置かれた環境や学びに関して、率直な質問が多く挙がった。
参加者からは、講師架蔵の資料を回覧したことで、より興味が広がった、これまでほとんど取り上げられることのなかった明治期の女性たちの先駆的活躍に興味を覚えた、続編を期待する、といった声が聞かれた。
|